筋力トレーニングを始める方には、「引き締まったカラダを手に入れたい!」「体力をつけたい!」などの熱い思いがあります。そして、それと同時に、「できるだけ早く!!」という思いもあるのではないでしょうか。
目標達成のために、筋トレを毎日頑張ろうと思っている方も多いはず。しかし最近は、筋トレを毎日するのは逆効果だという言葉を耳にすることもあります。果たしてどちらが正解なのでしょうか。
本記事では、「筋トレは毎日やれば早く効果が出るものなのか?」「より効果を上げる方法はあるのか?」ということについて、科学的根拠をもとに解説していきます。
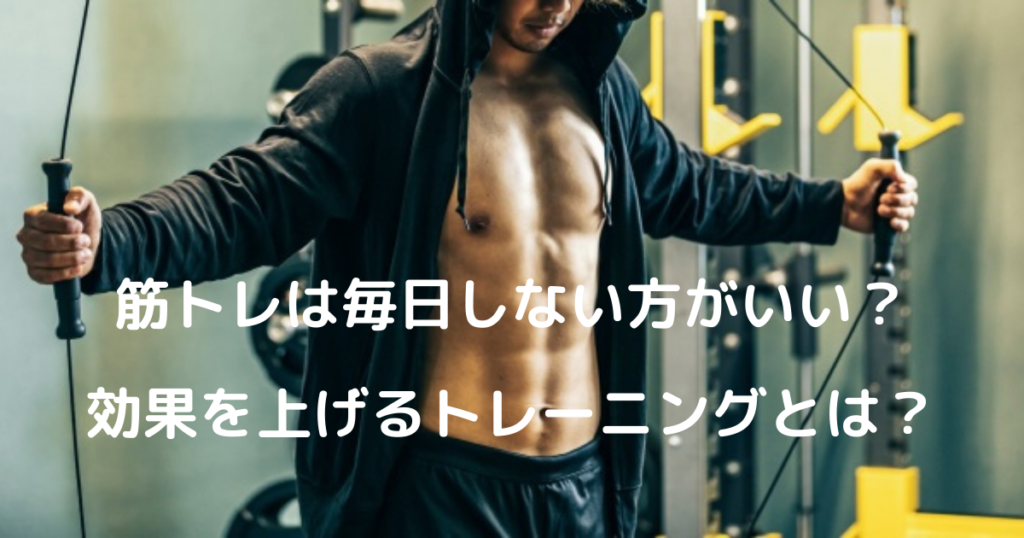
結論:筋トレを毎日するなら、部位のローテーションが効率的!
筋トレは毎日しない方が良いというのは、半分正解で、半分間違いです。
同じ部位の筋トレを毎日繰り返すことは逆効果になりますが、違う部位の筋トレを毎日ローテーションすることは効率的なボディメイクに繋がります。
下記では、その根拠となる「筋肉の超回復理論」と、トレーニングスケジュールの組み立て方について説明します。
筋肉を育てるのは休息
筋肉の超回復理論
なぜ同じ部位の筋トレを毎日繰り返すことが逆効果になるのか?
それは、筋肉が強くなる過程を知ることで理解できます。
1.筋トレによって筋組織が破壊される。
ある程度負荷のかかる運動をすると、筋肉痛を生じることがあります。これが、運動によって筋組織が破壊された状態です。
2.休息によって筋組織が修復される。
運動によって破壊された筋組織は、適度な休息や栄養によって回復していきます。その時、次回はこの負荷に耐えられるようにしようと、以前より強く大きく回復するのです。
これを「筋肉の超回復理論」と言います。
このように、筋肉は筋トレによってのみ強くなるわけではなく、休息を取り入れることでより強く大きくなります。同じ部位の筋トレを毎日繰り返すということは、この休息の機会を失うということなので、逆効果になるのです。
筋肉の超回復には24〜72時間の休息が必要
繰り返しますが、大切なのは、「筋肉は休息によってより強く大きく修復される」ということ。
特に筋トレを始めたばかりだと、「毎日休まずがんばって、早く理想のカラダを手に入れるぞ!」と気合が入ってしまいがちですが、休息がなければ十分な回復は見込めません。むしろ、回復を妨げ、筋トレの効果を低減させてしまいます。
超回復にかかる期間は、個人の筋トレ経験や筋力、筋トレの負荷や部位によって異なりますが、一般的には筋組織の損傷後24〜72時間と言われています。その間は筋肉を休ませ、栄養を与えることが必要です。
超回復に要する時間を考えると、同一部位の筋トレは週に2〜3日(1日やって2〜3日休む)程度がおすすめ。
では、その他の日はよく食べよく寝ていればいいのかというと、そうではありません。
そんなことをしていると脂肪はなかなか落ちませんし、体力もなかなかつきませんよね。何より、筋トレが生活の一部になりにくいので続けることが難しくなります。
筋トレを毎日の習慣にして効果を上げるためには、筋トレする部位をローテーションすることがおすすめです。
効果を上げるトレーニングを組み立てる
分割法
筋トレのスケジュールを組み立てる方法としては、分割法が有効です。
分割法とは、身体の部位を分割してトレーニング日を分けるトレーニング方法のこと。
日によって鍛える部位と休める部位をコントロールすることができるため、筋肉の超回復理論を基にトレーニングするにはうってつけの方法と言えます。
分割の種類は多様で、2〜5分割にするのが一般的ですが、その内4〜5分割については上級者向けとなりますので、まずは2〜3分割で取り組むのがおすすめです。
分割数は、週に何日やるか、1日やって何日休むか、などによって決めると、週間スケジュールが組み立てやすいでしょう。
例えば、週に6日、1日やって3日休むとすると、3分割が適当です。週に5日の場合はやや変則的となりますが、余裕のあるスケジュールで取り組むことができます。
週に3〜4日の場合は2分割が適当です。
週6日:①→②→③→休→①→②→③
週5日:①→②→③→休→①→②→休
週4日:①→休→②→休→①→休→②
週3日:①→休→②→休→①→休→休
2分割の分け方
1.上半身と下半身
身体を2分割にする分かりやすい分け方として、上半身と下半身に分ける方法があります。
上半身は、肩・背中・胸・腕、下半身は足です。
上半身の方が種目が多くなるため、日によって時間や疲労の偏りが大きくなりそうですが、その分体幹トレーニングを加減するなどして調整することで対応可能です。
2.プレス系(押す)とプル系(引く)
プレス系の種目とプル系の種目で分ける方法もあります。
プレス系は主に身体の前面にある筋肉を使います。
上半身では大胸筋や上腕三頭筋です。種目としては、ベンチプレス、ダンベルフライ、ショルダープレスなど。
下半身では大腿四頭筋です。種目としては、レッグプレスやレッグエクステンションなど。
プル系は主に身体の後面にある筋肉を使います。
上半身では広背筋や上腕二頭筋です。種目としては、デッドリフト、ラットプルダウン、ダンベルカールなど。
下半身ではハムストリングスです。種目としてはレッグカールなど。
3分割の分け方
1.プレス系(押す)とプル系(引く)とレッグ(脚)
2分割の分け方では、上半身と下半身を合わせてプレス系とプル系に分けましたが、3分割の分け方では、上半身をプレス系とプル系に分けて、下半身はまとめてトレーニングするという方法があります。
この方法のメリットは、分け方が分かりやすいことです。
上半身の押す運動と引く運動と脚の運動、という単純明快な分け方なので、初心者でもイメージがしやすく、種目を選びやすいと思います。
この方法のデメリットは、特定の部位に疲労が溜まりやすいことです。
同日に同一筋肉・同一方向の種目を繰り返すことになるため、種目を重ねるごとに疲労が溜まり、パフォーマンスが低下して思うような効果を得られないということが考えられます。
2.上半身の大筋群、上半身の小筋群、脚
この分け方では、運動の方向ではなく、筋肉のサイズを考慮します。
具体的には、大胸筋や広背筋・脊柱起立筋などの大筋群、上腕三頭筋や上腕二頭筋などの小筋群、下半身という分け方です。
この方法のメリットは、特定の部位に負担が偏らないことです。
同日に行う運動をプレス系とプル系に分散して、身体の前後面にある筋肉をバランス良くトレーニングすることになるため、筋肉疲労がパフォーマンスに与える影響を最小限にすることができます。
この方法のデメリットは、分け方がやや複雑になることです。
どの筋肉が大筋群あるいは小筋群に分類されるのか、それらをトレーニングするのはどの種目なのか、などの知識が必要となりますので、初心者にはややハードルが高いかもしれません。
おさらい
●筋トレで破壊された組織が、休息で修復されることで、筋肉が育つ。
●同一部位の筋トレは、1日やって2〜3日休む程度がおすすめ。
●筋トレを毎日の習慣にして効果を上げるため、分割法を活用してスケジュールを組み立てる。
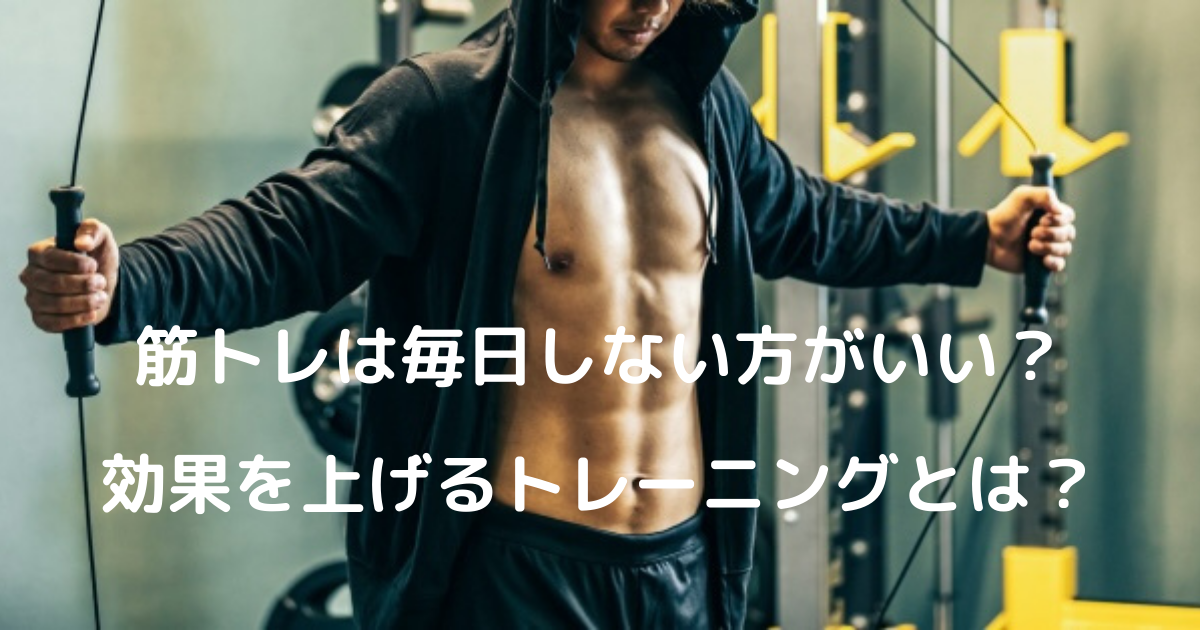
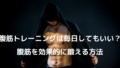
コメント